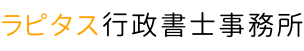行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法的に保護し、その方の財産管理や身上監護を支援するための仕組みです。この制度は、大きく「法定後見」と「任意後見」の2つに分類されます。
どちらも根底にある目的は同じですが、「利用を開始するタイミング」と「後見人を選ぶ方法」に決定的な違いがあります。
まず、法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。認知症の発症や病気・事故などにより、本人が自力で財産管理や契約行為を行うことが困難になった後に利用されます。
後見人の選任は家庭裁判所への申立てによって行われ、裁判所が本人の状況を精査したうえで、最適な人物(弁護士、司法書士、行政書士などの専門職を含む)を後見人として選びます。そのため、必ずしも家族の希望通りの人物が選ばれるとは限りません。
一方、任意後見制度は、本人がまだ元気で十分な判断能力があるうちに、将来の財産管理や身上監護を誰に、どのように任せるかを自らの意思で決めておく制度です。問題が起きる前の「予防的な制度」として利用されます。
本人は「任意後見受任者」を自ら選び、公正証書によって契約を締結します。そして、本人の判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申し立てを行い、「任意後見監督人」が選任されることで契約の効力が発生し、制度が開始されます。
自分の人生を誰に託し、どのような財産管理を任せるかをすべて自分の意思で決められる点が、任意後見制度の大きな特徴です。