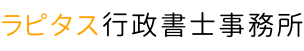行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
建設業法は戦後間もない昭和24年に制定され戦後復興事業や占領軍関連工事の急増とそれに伴う弊害を回避する背景で成立しました。時代とともに発注者の要請や技術力の向上等により工事の内容が変わっていることもあり建設工事に該当するかしないかというのは意外と判断が難しい場合があるようです。建物を建てるということの特徴は様々な建材が合わさって最終的に建物として土地に定着することにあります。建物は日本の不動産制度により特別に「建物」として独立の不動産と言えますがそれ以外の定着物(民法86条)は土地の定着物となります。(石垣や木、移転困難な庭石など)したがって、手を加えることによって最終的に「土地若しくは建物に定着したかどうか」が建設工事の判断基準の一つになるかもしれないですね。
例えば、剪定作業のみをする場合は土地・建物に材料を定着させる行為は含まれないので一般的には工事とは言えず、またいわゆる「人工出し」(職員を現場に派遣し労働力を提供すること)や「人夫出し」(技術者を現場に派遣すること)そのものは請負契約に該当しないので工事に該当するとは言えません。さらに保守点検作業などのための維持管理も工事に該当するとは言えません。
上記の例とは真逆に後述する内容については将来大きな問題を引きおこす恐れがあるため、建設業法上、明確に区別して分析する必要があるかと思います。例えば軽微な建設工事(法3条1項ただし書)に該当するのか。許可が必要な建設工事に該当するのか。兼業と扱うべきなのか(財務諸表で主に影響があるため)。経営業務の管理責任者や専任技術者の経験性の裏付けとなるか。などが挙げられます。また建設業許可申請制度の後に控えている経営事項審査制度や入札制度でも完成工事高に工事以外の売上が入っていないか。入札における「工事」以外(物品や業務委託など)と混同はないかなども同様でしっかりと確認をする必要があります。