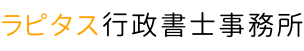行政書士 西浦 邦子
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会阪神支部
この記事の執筆者:行政書士 西浦 邦子
一般民事に精通した法の知識と実務経験で、行政書士業務を行っております。建設業許認可申請全般のサポート業務について許可取得のご相談から作成までワンストップで対応させていただいております。LGBTQなどのマイノリティと周囲の方のサポートも行っております。
目次
事前の現地調査は必要不可欠
相続土地国庫帰属制度には国側が引き取ることができない土地の要件があるため、その対象外となれば「不承認」となっていまい、「審査手数料(14,000円)」や承認申請のために要した労力についても全て無駄になってしまうので慎重な判断が必要です。それにより「現地調査」をしないとわからないことも多く、また現地の写真等は必須書類となっているので「現地へ確認しに行く」ことは必要不可欠なことです。
遺言書作成前に相続土地国庫帰属制度を利用する
「相続土地国庫帰属制度」は相続の時期は問われません。そのため必ずしも所有者が亡くならないと利用できないわけではありません。既に相続原因で所有している所有者の方もこの制度を利用することができます。特に遺言書作成をされている方は将来、相続人となる方の負担を軽減したいと考えている場合は前もってこの制度を利用してみても良いかもしれません。
二筆以上の場合、負担金の特例を利用することができる
農地・森林などの相続人の多くは複数筆の土地を相続している場合が多くあります。その場合この制度の特例として「隣接する二筆以上の土地の負担金算定特例」を利用することができます。この特例を利用することにより二筆以上の土地を一筆とみなすことにより国庫への負担金を減額することができる場合があります。その二筆以上の土地が隣接しているかどうかかつ隣接する土地の種目が同じである場合の確認などが重要になります。
囲繞地(いにょうち)の土地の場合、隣地とあわせて利用する
公道に面していない囲繞地(いにょうち)や里道と呼ばれる土地が多くあります。この場合法務大臣による要件審査によりこの制度を利用することができませんが、隣接する土地が公道等に接している土地であって併せて申請する場合は相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。ただし、条件として、原則隣接する土地所有者の所有原因が相続である場合に限ります。
共有者に相続原因の者がいる場合に利用する
所有者ご自身の所有原因が売買など相続以外の場合でも、共有者に相続原因の者がいれば相続土地国庫帰属制度を利用することができます。ただし、その共有者全員の同意が必要となります。